「電気工事士」—社会を支える、誇り高い専門職。その仕事に魅力を感じながらも、あなたの心の中に、どうしても拭えない一つの言葉がありませんか?
それは、「感電」という、原始的で、本能的な恐怖を呼び起こす言葉です。
「ビリっとくる痛み」「体が動かなくなる痺れ」「火花が散る光景」…
特に、私たちが手掛ける仕事の一つである「強電」という言葉の響きは、その不安をさらに増幅させるかもしれません。「高電圧を扱うなんて、本当に安全なのか?」「未経験の自分が、取り返しのつかないミスをしたら…?」
その不安、痛いほどよく分かります。だからこそ、この記事では一切の建前なく、電気工事のプロである私たち有限会社小峰電気が、その「リスクの真実」と「絶対安全の哲学」について、真正面からお話しします。
最初に「弱電」と「強電」の感電リスクの違いを明確にし、その上で、たとえリスクレベルの高い「強電」の現場であっても、私たちがなぜ「絶対安全」を実現できるのか。プロの現場のリアルを、具体的にお伝えします。
【リスクの真実】「弱電」と「強電」で、危険レベルは天と地ほど違う

まず、あなたの不安を正しく整理するために、電気工事の2つの世界を「感電リスク」という、ただ一つの視点から切り分けてみましょう。
弱電(じゃくでん)工事のリスク —【レベル1:ほぼゼロ】
扱う電気
主に48V未満の低電圧。これは、インターネットのデータや防犯カメラの映像といった「情報・信号」を伝えるための電気です。
感電のリスクは?
基本的に、人体に危険を及ぼすことはありません。 人間の体が感電の危険をはっきりと感じるのは、一般的に50V前後からと言われています。弱電で扱う電圧はそれよりも低いため、理論上、体にダメージを与えるほどのエネルギーを持っていないのです。乾電池を舐めた時に感じるピリピリ感や、冬場の静電気に近い、と言えばイメージしやすいかもしれません。怪我につながるような危険はまずなく、安全に作業できる分野です。
強電(きょうでん)工事のリスク —【レベル5:最大級の警戒が必要】
扱う電気
100V、200V、そして時には6600Vにも達する高電圧。これは、照明や機械を動かすための「エネルギー」そのものです。
感電のリスクは?
本質的に、極めて高いリスクが存在します。 はっきりと言いますが、もし電気が流れている状態で誤って触れてしまえば、重篤な怪我、体に癒えない後遺症を残す可能性、そして最悪の場合、命を落とす危険性があります。
「やはり、強電は危険な仕事じゃないか!」
はい、その通りです。強電が持つエネルギーは、人間が安易に触れていいものではありません。私たちは、電気を「敬意を払うべき、力強いパートナー」として捉えています。そして、その強大な力を知り尽くしているからこそ、それを完璧にコントロールし、リスクをゼロにするための「技術」と「哲学」を、何よりも大切にしているのです。
【絶対安全の哲学】なぜプロの「強電」現場は、”絶対”に安全なのか
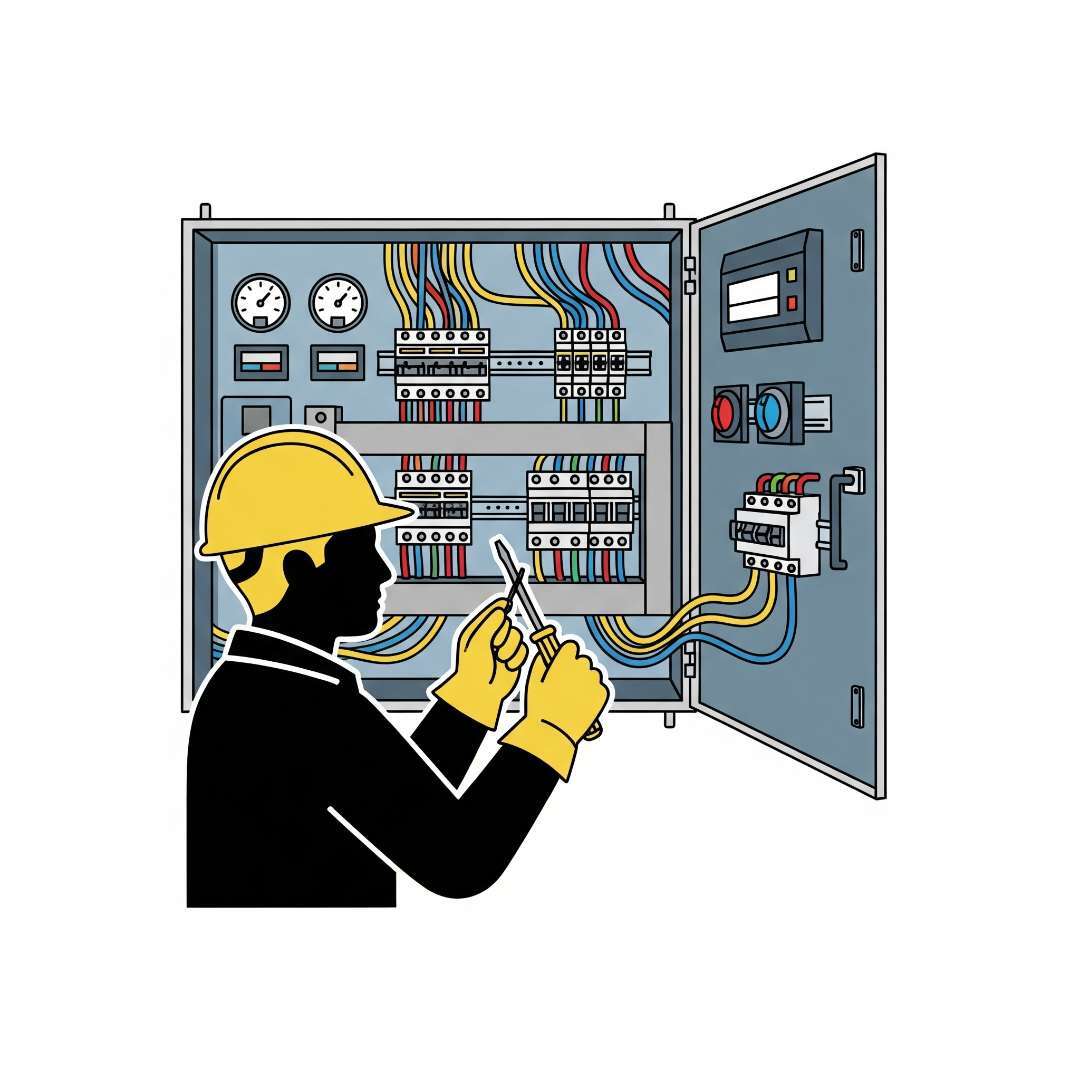
危険なのは、電気そのものではありません。危険なのは、ルールを知らないこと、そしてルールを守らないことです。有限会社小峰電気の現場では、たとえリスクレベルの高い強電工事であっても、あなたの安全を守るための「仕組み」が、会社の文化として隅々にまで浸透しています。
1. 大原則:『停電作業の絶対徹底』— そもそも、電気は流さない
これが、私たちの安全管理における揺るぎない憲法です。電気工事は、必ず作業箇所の電源を落とし、電気が一切流れていない「停電状態」で行う。これは、絶対のルールです。そして、そのプロセスは極めて厳格です。
ステップ①【遮断】: 主電源や該当箇所のブレーカーを確実に「切」にします。
ステップ②【施錠・表示】: 誰かが誤って電源を「入」にしてしまう事故を防ぐため、ブレーカーに物理的な鍵をかける「ロックアウト」や、「作業中!送電禁止!」と書かれた札をかける「タギング」を行います。
ステップ③【検電】: 専用の器具(検電器)を使い、「本当に電気が来ていないか」を作業箇所で直接確認します。まず検電器自体が正常に作動するかをテストし、その後、複数人で、複数の箇所を、指差しと声出しでダブルチェック、トリプルチェックします。
この全ステップが完了するまで、誰も電線に指一本触れることはありません。未経験のあなたに、このプロセスを省略したまま作業をさせることは、絶対に、100%ありません。
2. 鉄壁の防護:『個人用保護具(PPE)』— あなたの身を守る最後の砦
万が一、億が一の事態に備え、身を守るための装備にも一切の妥協はありません。
絶縁保護具: 高電圧を扱う現場では、電気を全く通さない特殊なゴムで作られた「絶縁手袋」や「絶縁長靴」の着用が義務付けられています。
これらはただのゴム手袋ではありません。使用前には必ず空気を入れて、目に見えないピンホール(小さな穴)が開いていないかを全員がチェックします。この一手間が、命を守ります。
ヘルメットと安全靴: 頭部を守るヘルメットの「あご紐」をしっかり締めること。足元を釘や落下物から守る安全靴を履くこと。当たり前ですが、この当たり前を全員が徹底することが、プロの現場です。
3. ヒューマンエラーの撲滅:『チームで行う危険予知(KY)活動』
事故の最大の原因は、「これくらい大丈夫だろう」という個人の慣れや油断です。それを組織的に防ぐのが、毎日の作業前に必ず行う「危険予知(KY)活動」です。
これは形式的な朝礼ではありません。その日の作業内容に基づき、「今日の現場に潜む危険は何か?」を全員で具体的に洗い出し、対策を共有する、極めて実践的なミーティングです。
「今日は高所での作業になるから、工具の落下防止対策を再確認しよう」
「雨上がりで足場が滑りやすい。昇り降りの際は三点支持を徹底しよう」
「新しい資材が搬入されて通路が狭くなっている。運搬時の接触事故に注意しよう」
このように、チーム全員が同じ危険イメージを持つことで、一人の見落としを仲間がカバーできる、強固な安全体制を築いています。
未経験のあなたへ。小峰電気が約束する、一番大切なこと
私たち小標電気は、あなたに一流の技術を教えます。しかし、それよりも先に、そして何よりも大切に教えるのは「安全」です。なぜなら、あなたの命と健康を守ることこそが、会社と、あなたを指導する先輩たちの、最も重要な社会的責任だと信じているからです。
技術は、時間をかければ必ず身につきます。仕事で失敗することもあるでしょう。しかし、安全に関する失敗だけは、絶対にあってはなりません。
だからこそ、私たちは未経験のあなたを、決して一人にはしません。
手順が分からなければ、分かるまで教えます。
作業に不安を感じれば、あなたの不安がなくなるまで、別の作業を任せます。
「怖い」と感じるあなたの感覚を、私たちは「安全に対する健全なセンサー」として尊重します。
危険なのは、仕事そのものではなく、安全を軽んじる心です。
小峰電気の現場には、その心の隙が生まれる余地はありません。私たちの仕事のリアルを、ぜひ一度見に来てください。そこには、あなたの不安を安心へと変える、プロフェッショナルたちの真摯な姿があるはずです。
▼有限会社小峰電気 採用情報はこちら


